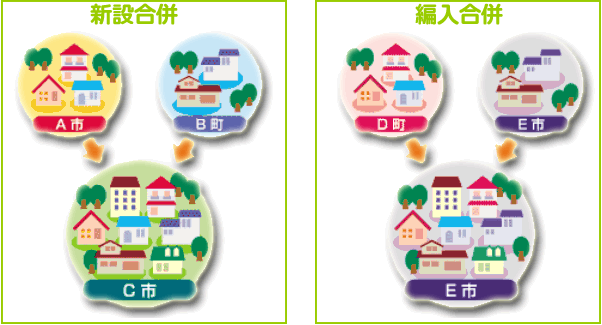昭和30年代以降の高度経済成長は、国民の生活水準の向上やモータリゼーションの進行をもたらし、それにより人々の日常生活圏は拡大し、従来の市町村の枠組みを超えた広域行政の要請が意識されるようになり、市町村合併の動きが各地で見られるようになってきました。
こうした動きに対処するため、昭和40年に10年間の時限立法として「市町村合併の特例に関する法律」が施行され、昭和50年、昭和60年、平成7年にそれぞれ10年間ずつ延長し、平成11年には合併支援の特例措置が大幅に拡充されました。現在、この法律の有効期限は、平成17年3月31日となっています。
少子・高齢化や地方分権など、市町村行政を取り巻く情勢が大きく変化する中で、基礎的自治体として総合的に住民サービスの提供の責務を負う市町村は、その行財政基盤の強化や多様化・高度化する住民ニーズに対応した、より高度な行政サービスの提供を求められていることから、今まで以上に、市町村合併の推進が強く求められています。
少子・高齢化の進展 [合併によってA]
地方自治体にとって、ますます進展する少子・高齢化は、納税者数や生産年齢層の減少に伴う地方税収の減少や、高齢者の医療や介護・福祉サービスにかかる歳出の増加を意味します。
このため、十分な財政力や、高齢者の生活を支える専門家を含めた人材の確保が必要となります。
日常の行動範囲の拡大 [合併によってB]
交通・情報手段の発達などによって、通勤・通学や買い物、通院など、住民の日常生活の行動範囲は、現在の市町村の区域を越えて飛躍的に拡大しています。
これに伴い、現在の市町村の区域を越えた行政サービスの提供や、効率的な公共施設の配置、広域的なまちづくりなど、広域化した生活圏への対応が求められています。
地方分権社会や多様化する住民ニーズへの対応 [合併によってC]
地方分権が進むなか、住民に最も身近な市町村が主体となって、きめ細かな行政サービスの提供や個性豊かなまちづくりを行っていくことが求められています。
また、介護、福祉、保健、医療、環境問題、情報化などの新たな行政課題に対応するために、より専門的な知識や技術を持った職員が必要となります。
国・地方の厳しい財政状況への対応 [合併によってD]
長引く景気低迷のため、国・地方は大変厳しい財政状況にあります。今後の経済の大幅な成長が難しく、少子・高齢化の進展により、ますます財政状況が厳しくなるものと予想されるなか、行政サービスを安定的に提供していくためには、行政の効率化を図っていくことが急務となっています。
上へ戻る |